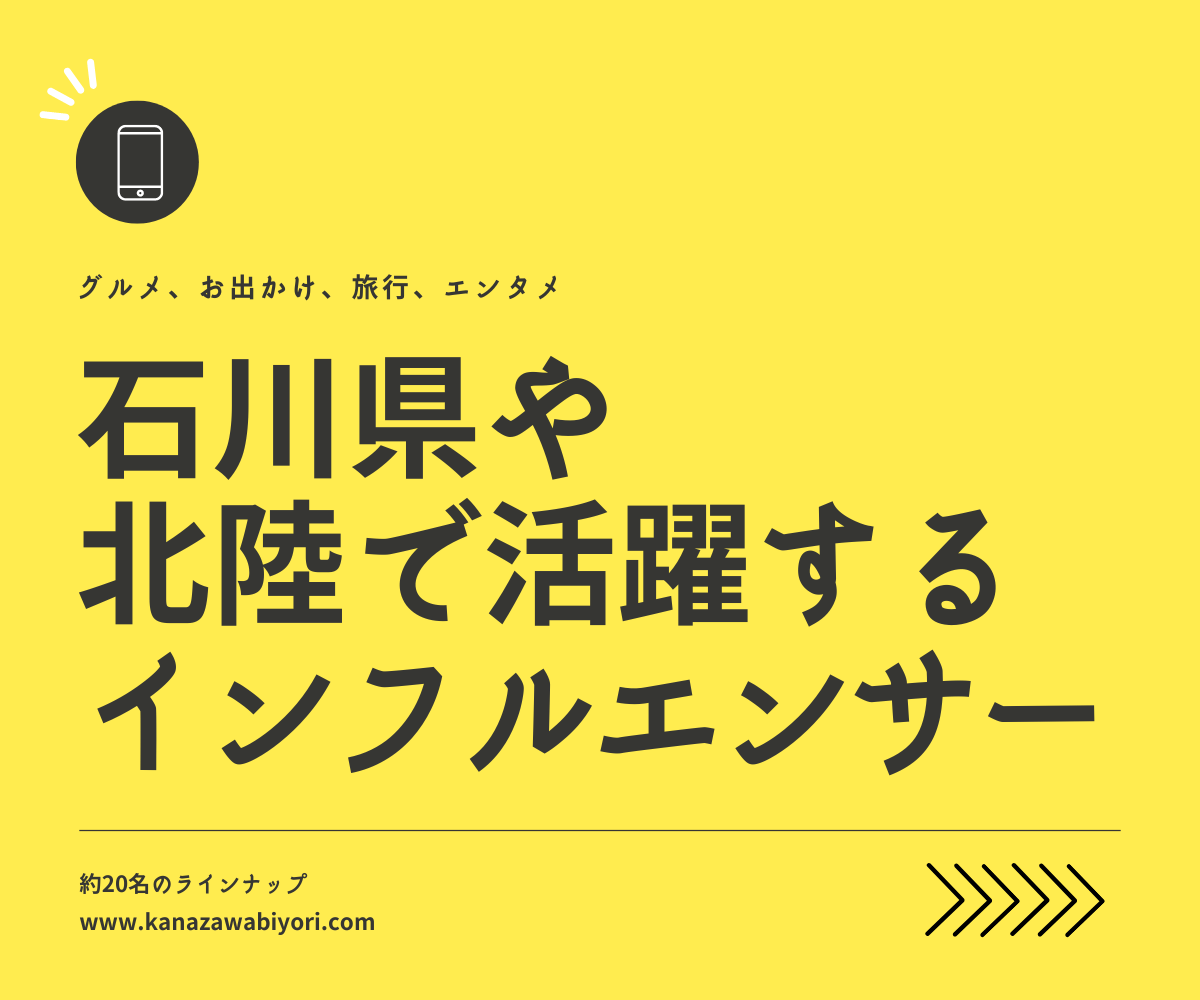【農援ラボ|岡元農場】地域の宝・加賀丸いもを次世代へ。親子でつなぐ継承のバトン
2025年3月10日(月) | テーマ/エトセトラ


2024年11月、岡元農場では加賀丸いもの収穫作業が最盛期を迎えていた。トラクターをゆっくり前進させながら高く盛った畝を掘り起こし、姿があらわになった丸いもをひとつずつ手作業で拾い上げていく。
「父の話では今年の収穫はここ20年で一番出来がいいらしいです。芋が大きくなる時期に適度に雨が降ったのがよかったのかもしれません」
岡元望さんは軽トラックに山積みしたコンテナから大ぶりの丸いもを手に取ると、こちらによく見えるように笑顔で差し出した。

石川県の能美・小松両市で栽培されている加賀丸いも。山芋の一種で、農林水産省の「地理的表示(GI)」に登録される地域特産物だ。岡元家は江戸時代から続くとされる米農家だが、丸いもの栽培は岡元さんの父親が初めて手掛けた。稲作に並ぶ事業の柱を作りたいと、25年ほど前に地域の特産物であった加賀丸いもに白羽の矢を立てたのだという。
「小学生の時には地域を学ぶ教科書に父が掲載されていて、子どもながらに誇らしい気持ちでしたね。丸いもの種芋の植え付けや収穫を体験する小学校の課外授業もうちでやったんですよ」
進路について父親から強制されることは一切なかったものの、岡元さんのそうした原体験は自然と家業への前向きな心を培った。大学で農学を専攻し、流通の仕組みを学ぶべく東京の食品商社に就職。そして2023年、Uターンした岡元さんは晴れて父親が代表を務める岡元農場に参画し、これまでの知見を米や丸いもづくりに生かすこととなった。

加賀丸いもは、その名の通り丸い形と、すりおろした際にひっくり返しても皿から落ちないほどの強い粘りが特徴。高級品のためお歳暮などの贈答用や料亭の需要が多いが、その歴史を紐解けば、大正時代に澤田仁三松(にさまつ)氏と秋田忠作氏が三重県の伊勢いもという山芋を持ち帰って栽培したことにルーツがあるといわれている。
「ただ当時は丸い形ではなかったそうなんです」と岡元さん。丸い形に変化したのは昭和9年に発生した手取川流域史上最大となる大洪水がきっかけだった。もともと粘土質だった田んぼに上流から流れてきた土砂が大量に流入し、土壌が変化したことで丸い形の山芋が栽培できるようになったのだ。
「重たい石が沈殿した川沿いも、泥ばかりが流れてきた川から離れた場所も丸くはならない。丸いもが丸く育つのは、砂と泥が混ざりあったちょうど中間のエリアだけなんです」

まさに自然がもたらした地域の宝といえる加賀丸いも。しかし現実は厳しく、加賀丸いもの生産農家は現在に至るまで減少の一途を辿っているという。高齢化に加え、栽培にかかる手間の多さに要因があると岡元さんは指摘する。
「山芋は本来、山で育つもので、平地で栽培するにはさまざまな手入れが必要になります。山の環境を再現するために畝を高くして水はけをよくし、芽が出てからは山の木の代わりに支柱を立ててきちんと弦が巻き付くように誘導しなくてはならない。連作障害を避けるため、同じ圃場では3年に一度しか栽培できない点もネックです」

さらに形の美醜で価値が大きく左右される商品特性も生産者にとっては諸刃の剣だ。栽培にまつわるさまざまな研究や経験則からある程度の道筋は立てられるものの、結局丸いもは掘り起こすまで土の中。出来不出来はある種のギャンブルに近いのだ。
「丸いもと聞いて一般に想像されるような形の整ったものは、全収量のごくわずかに過ぎません」と岡元さん。その一方で形が不出来で一般販売できない丸いもは、加工原料として業者に卸すほかないのだという。食味には問題がないのに関わらず、である。
生産者の減少に、生産に付随する多くのコスト。そして高付加価値品であるがゆえの限られた需要。加賀丸いもを取り巻く課題はどれも一筋縄ではいかないものばかりだ。それでも複雑に絡み合った糸をほどくように、ひとつずつ課題に向き合うことが最善策だと岡元さんは考える。

「ひとつの活路は個人向けの需要の拡大。そのためには一般の方々により認知してもらう必要があります。以前全国区のTVで紹介されたことで遠方からの注文が増えて、その後も受注が継続しているというよい循環もできている。丸いもの魅力がきちんと伝われば、掘り起こせる需要はあると実感しています」
世代交代や地域特産物への興味などをきっかけに、少しずつ周りに若い生産者が増えてきている流れも岡元さんにとっては心強い。「100年以上にわたって地域に愛されてきた加賀丸いもを守りたい」。若干29歳の若者が手にするバトンはずしりと重たいが、多くの同志とともに未来へ継いでくれることを願いたい。

■岡元農場
住所/石川県能美市福岡町ロ184
電話番号/0761-55-0668
公式サイト https://okamotonojo.com/