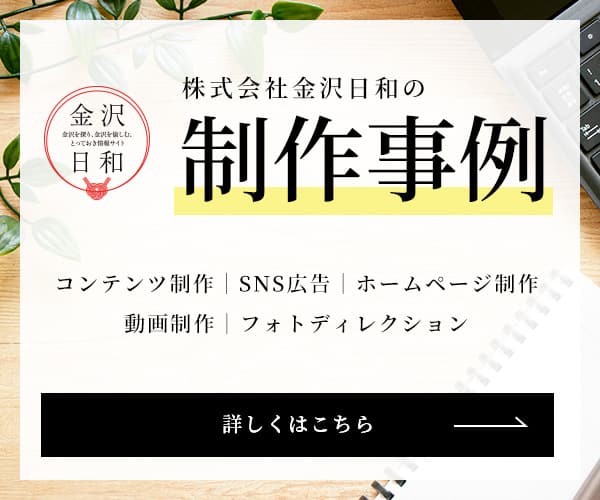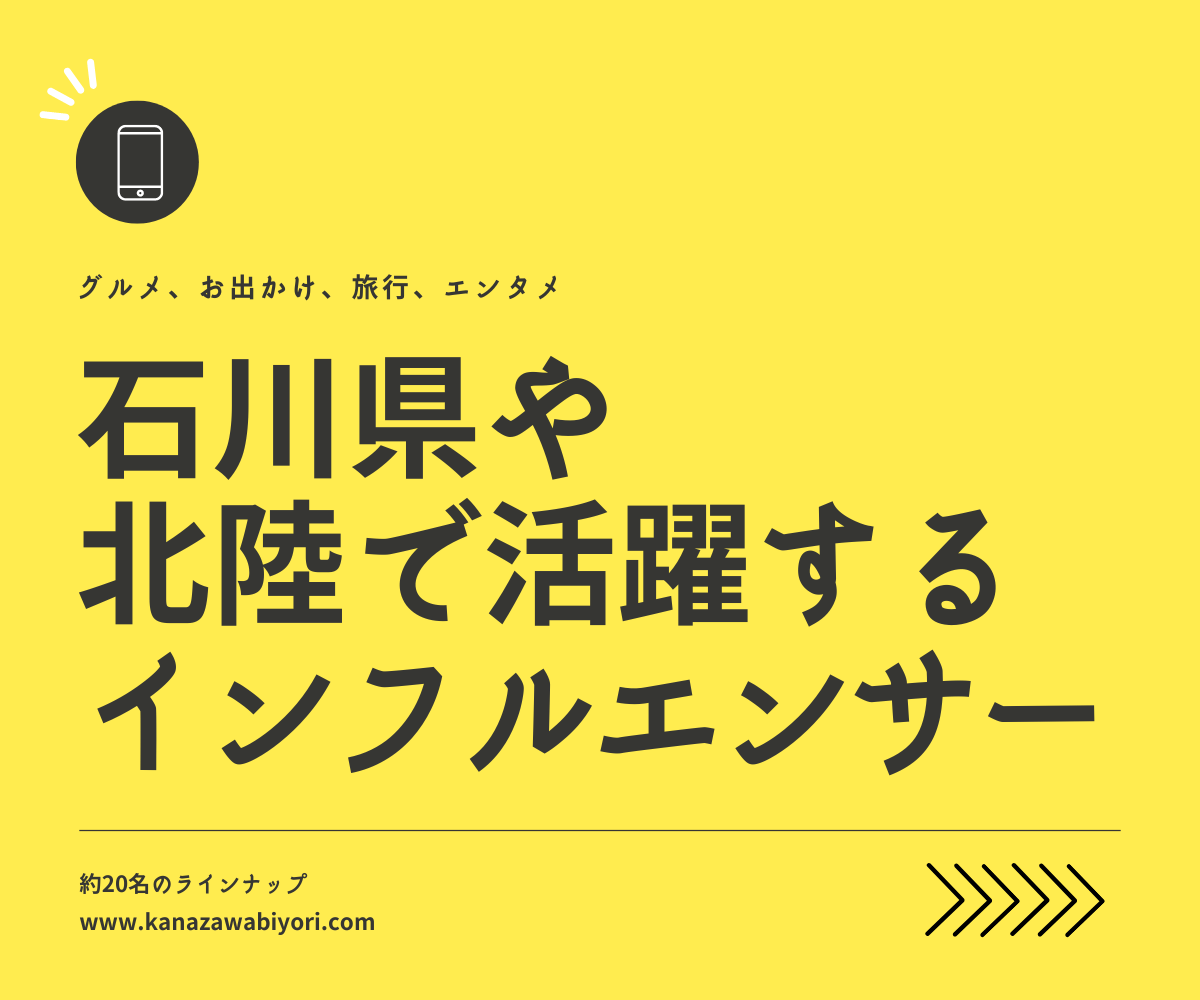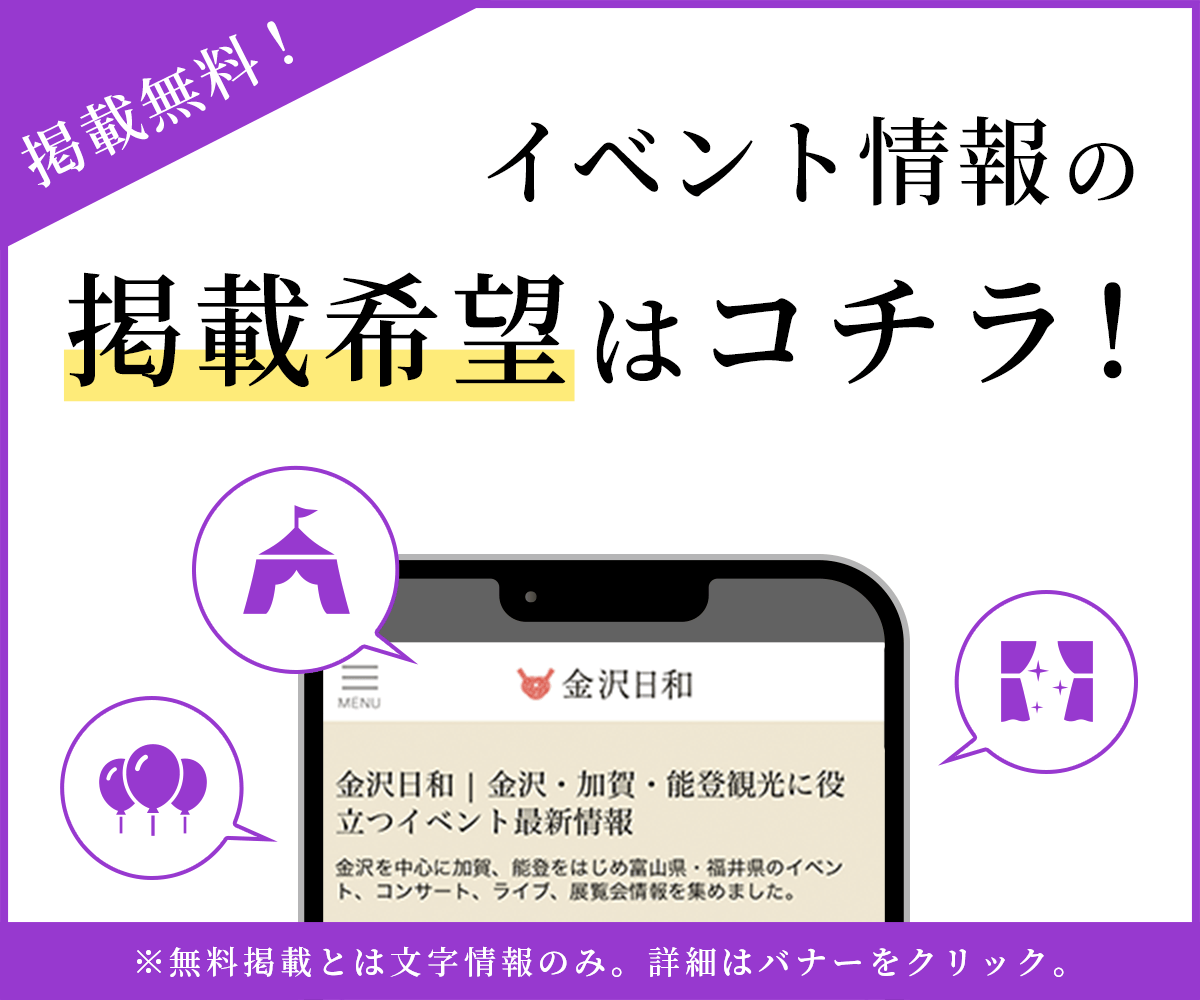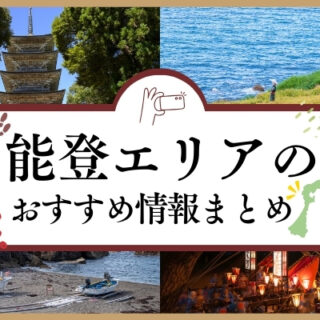ふるや紙
2014年5月15日(木) | テーマ/金沢の雑学

金沢は古くから金箔の生産がとても盛んです。
現在でも全国生産量の99%を生産しています。
その金箔を作る際に欠かせないものが「箔打紙」。
「澄」と呼ばれる金と金の間に挟みこむ和紙のことで、職人の手により、藁の灰汁や柿渋などに浸した和紙を叩いて作られています。紙なので一度使用するとボロボロになってしまうのではと考えてしまいますが、実はとても強度があるそうで、何度も使われます。
そして「箔打紙」として使えなくなったものが、今回のタイトルである「ふるや紙」となります。
既にお気付きの方もおられるかもしれませんが、
「あぶらとり紙」の原型になったもので、当時はすごく貴重だったようです。
今でも実際に金箔製造で生まれた「ふるや紙」は、販売されており、
中には職人が記した数字や文字、また少し金がついているものもあったりします。
実際に使ってみると、ほのかな香りと柔らかい使い心地で、とても上品な印象を受けました。
その他の同じテーマ記事
【金沢のお正月】金沢の正月に欠かせない占い系縁起菓子「辻占(つじうら)」
(写真提供:金沢市) 金沢のお正月にいただく和菓子の代表・福梅(ふくうめ)と並んで有名なのが「辻(続きを読む)
【金沢のお正月】福徳(ふっとく)せんべい
2025年もあとわずか。イベントを一つひとつ終え、お正月準備も万全という方も多いのではないでしょうか(続きを読む)
【金沢のお正月】全国的に珍しい石川県の「紅白」鏡餅。
石川県民の多くは紅白の鏡餅を飾ります。そんなの当たり前でしょと思った県民の皆さん、実は全国的には上下(続きを読む)
【金沢のお正月】金沢のお正月に欠かせない祝菓「福梅(ふくうめ)」
12月になると、金沢近郊の和菓子店には正月の和菓子「福梅(ふくうめ)」が並びます。 毎年決まった店(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】火除地(ひよけち)とするために植えられた柿の木が由来!?『柿木畠振興会』
火事が多かった江戸時代、防火用の空地「火除地(ひよけち)」として植えられた柿の木が、この町名の由来と(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】約400年もの歴史を誇る中心街の一つ『竪町商店街振興組合』
竪町は金沢で約400年もの歴史を誇る中心街の一つ。全長430メートルの中央通りは「タテマチストリート(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】古さと新しさが調和した不思議な魅力を持つ『新竪町商店街』
レトロな雰囲気が漂う「新竪町商店街」。ここには骨董古美術品や異彩を放つギャラリー、若者に人気のこだわ(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】昭和の風情が残るレトロな外観の建物が立ち並ぶ『尾山神社前商店街』
加賀藩祖・前田利家公と正室おまつの方を祀る尾山神社。そのお膝元にある「尾山神社前商店街」は開設70余(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】日本三大名園の一つ・兼六園周辺で観光客をもてなす『金沢城兼六園商店会』
国の特別名勝に指定され、日本三大名園としても知られている兼六園。「金沢城兼六園商店会」は、そんな兼六(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】街の歴史を知る老舗と、若き経営者の店が混在する『新天地商店街振興組合』
複合商業施設『片町きらら』の裏通りに位置し、片町繁華街の活況の一翼を担う「新天地商店街」。商店街設立(続きを読む)